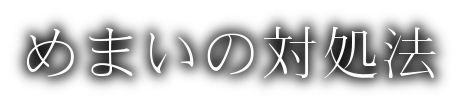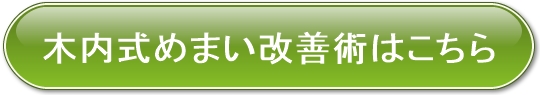めまいを起こすもっとも大きな要因はストレスと言われています。
ストレス自律神経の交感神経が過緊張状態になって、自律神経のバランスを乱し、めまいを引き起こす前庭神経を刺激するのです。
それでは、ストレスとは、具体的にどんなものがあるのでしょうか。
過度なストレスはよくないといわれますが、具体的にストレスとは何かというと、かなり複雑な話になってきます。
ここでは、めまいに関するストレスにしぼってご説明しましょう。
目次
ストレス社会のせい?めまいで病院を受診する人が急増
めまいが原因で病院を訪れる人は年々増加しています。
昭和10年代、30年代、50年代と、20年間隔で調べてみたところ、驁くべき結果が出ました。
昭和10年代を1としたら、30年代は3、50年代になると、さらに3倍の9へと急増していたのです。
この患者数の増加は、社会や生活の変化、なかでもストレスとの関係が考えられます。男女比では、昭和10年代の患者さんは、ほとんど、それこそ9割が男性でした。50年代になって男性6、女性4になってきて、その後、女性の患者さんがどんどん増えてきています。
いまでは女性6、男性4と女性の患者さんのほうが多くなっています。かつては女性の患者さんが少なかったのは、女性にストレスが少なかったというような、そんな単純な話ではないでしよう。
昭和10年代は一家の大黒柱は男性でした。男性が働いて家庭を支えていたので、「お父さんが倒れたら大変」ということで男性の受診が多かったのでしょう。
ではその頃の女性はというと、何か不調があっても「女の血の道」ということですまされていたのです。女性にとってはつらい時代でした。
ただ、やはりこれほど女性の患者さんが増えた背景には、女性の社会進出が進みそれに伴うストレスが増加したことが関係しているでしょう。
では、ストレスとはいったいなんだろうというと、誰もが思い浮かべるのは心理的な負担や心配事などのメンタルストレスでしょう。
めまいを引き起こすストレスは文明化のせい?

ただ、私たちが受けるストレスはそれだけではありません。気温や気圧の変化、大きな音、通常ではあり得ない加速度(飛行機や新幹線)など、これらすべてが生体にとってのストレスになってきます。
産業革命以降、私たち人類は便利さを求めた結果、体に負担のかかるストレスフルな生活になってきています。
飛行機や新幹線など高速で長距離を移動できるようになった一方で、内耳に負担がかかっています。ヘッドホンステレオなどを携帯して音楽を聞くツールの登場によって、どこでも好きな音量で音楽を楽しめるようになりましたが、あまり大きな音で聞いていると、 これも内耳に負担をかけてしまいます。
めまいを引き起こすメニエール病を「メニエライゼーション・イズ・シビライゼーション」(メニエール病化は文明化)と言った博士もいます。
要するに、文明が進歩することによってストレスが多くなり、メニエール病が増えて問題になってきたといくことです。
温度変化が体に負担
いまや生活に不可欠なエアコンも、私たちの体にはストレスとなります。
室内ではいつでも快適な温度のなかで過ごせますが、外気温はもちろん違います。ここ最近の温暖化で、 日本の夏はどんどん暑くなり、気温が高くなっているのはご存知のとおりです。
ある研究で、前日の気温との差が6度以上あると、カゼをひく割合が上昇することがわかっています。いわゆるカゼのウイルスがノドの粘膜についてカゼ症状を発するリスクは、 温度差6度以上で統計学的に有意な差が見られたそうです。
最近は35度を超える猛暑日も珍しくなくなってきました。エアコンの設定温度として推奨されているのは28度ですが、外気温がこれだけ高くなってしまうと、温度差を6度以内にするのは現実的な話ではないでしょう。
冬の暖房についても、同じことが言えます。 ただ、温度差が体へのストレスになっていて、それがめまいの要因となり得ることを知っておくべきです。
夏にエアコンを使わないというのは現実的ではありません。熱中症の心配もあります。例えば、温度が高くなる日中はエアコンを活用して、夜になって外気温が下がってきたらエアコンを止めて外気を入れてみるなど、無理のない範囲でエアコンと上手につきあうようにしてはいかがでしょうか。
ストレスを少なくするといっても、できるものもあるしできないものもあります。ただ、現代のストレスは減るどころか増えていく一方ですから、そういう社会に住んでいるということを理解して、受けるストレスを軽減する方策を考えて作戦をたてることが大切なのです。
大きな音が内耳にストレスに

大きな音も内耳へのストレスになり、めまいを誘発させます。
大きな音を聞き続けていると難聴になりやすく、そこからめまいを引き起こすことがわかっています。大きい音は内耳の有毛細胞を痛めつけます。
有毛細胞は生まれたときにはすでに備わっていて、時間の経過とともに傷み、減っていくだけの再生しない神経細胞です。衰える一方なのですから、できるだけ負担を軽くしたほうがいいに決まっています。
聴覚の優れたバンツー民族
1950年代のアメリカの学者べケシー博士が、太鼓すら持たないアフリカのバンツー民族という先住民の聴覚を調べました。なぜバンツー民族かというと、彼らが大きな音とは隔絶された社会で生活していたからです。
聴覚が非常に発達していて、野生動物が茂みを動くカサコソという音を聞き分けて狩猟するという狩猟民族です。
彼らの聴覚を調べるために、サッ力ー場ぐらいの広さのある広場で、彼らに見えないようにクギを一本地面に落としたところ、なんと彼らは、クギが砂の上に落ちたポ卜ンというかすかな音を聞き取ったのです。
聴覚に関しては、ヒ卜ではこれが最高ではないかと思います。なぜかというと、彼らはふだんから大きな音を聞いていないので、内耳の有毛細胞がダメージを受けていない。これが影響しているのだろうということです。
それに比べれば、現代人は生まれる前からさまざまな音にさらされ、耳元でドンチャ力、 ドンチャ力と大きな音を聞いています。これでは有毛細胞もすり減ってしまうでしょう。
胎児にもストレスになる
胎教で赤ちゃんに音楽を聞かせるといいといいますが、これは母親がリラックスしてそれが赤ちゃんによい影響をもたらすのでしょう。
解剖学で著名な京都大学名誉教授である故岡本道雄教授(1913〜2012)は、 授業のなかで「諸君らの妻が妊娠したら、怒らしてはいかん」とおっしゃっていました。
岡本道雄教授によると、妊婦がー日怒ると、胎児はオギャアと生まれてから3か月間に体験するストレスと同じくらいのダメージを受けるそうです。
胎児の脳はものすごい勢いで発達しているので、母親が怒ってアドレナリン過剰の状態になると、胎児に悪い影響が出てしまう。
「だから、諸君らの奥さんが妊娠したときには大事にして、怒らせないようにしたまえ」としうことだそうです。
胎教でいい音楽を聞いて母親がリラックスするのはいいのですが、あまり大きな音で聴かせるとかえって有毛細胞へのストレスとなります。
妊娠中はもちろん、ふだんから音楽を聞くときには音量に気をつけましょう。
ストレス由来のめまいを軽減する方法は?

できるだけストレスが少ない生活を送るためにどうすればいいのかを考えると、とてもシンプルな答えに行き着きました。
人間の生活は、習慣とか条件反射とか、そういった行為や行動の繰り返しです。
会社員なら朝起きて食事をして、職場に行って仕事をして、昼食を食べて、仕事をして、家に帰って夕食をとって、お風呂に入って眠る。ざっくりとしていますが、この流れを毎日反復することで成り立っているわけです。
めまいを引き起こすストレスの軽減には規則正しい生活
この毎日のルーチンから外れないようにすることは、 もっともストレスが少ない生活といっていいのではないでしょうか。
日常の規則性から逸脱することは、体には予測不可能なことであり、ストレスが多少なりともかかってきます。 ストレスを最小限にするためには、規則正しい生活を送る、これに尽きます。
ス卜レスの影響が少ない生活習慣
早寝、早起き、適切な食習慣など規則正しい生活を送るのはもちろん、自分の考え方や物事のとらえ方を変えることも大切です。がんばりすぎはス卜レスのもとです。
仕事や家事などをがんばりすぎる、責任感の強い人ほどストレスがたまりやすく、それに伴うめまいなどの症状が出やすくなってしまいます。
趣味や娯楽を楽しみ、 肩の力を抜くことを覚えましょう。ウォーキングのような有酸素運動もストレス解消になるのでおすすめです。
めまいを軽減する生活、5つのポイント
①規則正しい生活を送る
早めに帰宅して食事をすませ、早寝早起きを心がける。
②周囲の評価を気にしすぎない
仕事、家事を頑張りすぎない。完璧主義にならない。失敗を恐れない。
③悩みを相談する
相談事がなくても楽しく周りとおしゃべりを楽しむ。
④趣味や娯楽を楽しむ
旅行やスポーツ、家族や友人との食事、カラオケなどでストレス発散する。
⑤適度な運動をする
ウォーキング、ヨガ、ダンス、水泳などの有酸素運動がストレス軽減に有効。