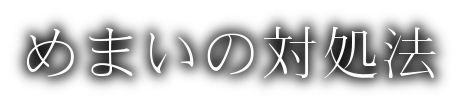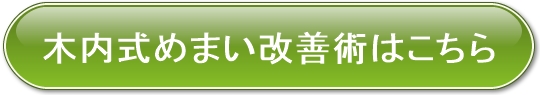まずはじめに、突然めまい発作が起こったときの対処法をお伝えします。
その後に、めまい対処法「予防編」として、めまいの長期的な予防の基本となる5つのポイントをご紹介します。
めまいに悩まされない生活を送るための参考になれば幸いです。
▼薬を飲む前に!お勧めのめまい改善法▼
目次
突然のめまい対処法

突然のめまいに襲われた方への対処法です。
めまい対処法①あわてない

いくら日常生活に注意しても、めまいが起こってしまうことはあります。
そんなとき、あわてたり、不安になったりしては、症状が落ち着くどころか悪化してしまうこともあります。
ここでは、めまいにおそわれたときの対処法について確認しておきましょう。
小脳や脳幹の出血など中枢系のめまいの場合は、頭を動かさず、すぐに救急車を呼ばなければなりませんが、それ以外はあわてることはありません。
突然のめまい発作の対処はあわてず騒がずが基本です。
動くとつらいので、めまいがらくになる姿勢を探して、発作が治まるまでは安静にしておきましょう。
内耳によるめまいの場合、異常があるほうの耳を下にするとめまいがひどくなるので、頭の向きを少しずつ変えて、どちらの向きが楽かをチェックして、らくな姿勢で安静にして過ごします。
めまい対処法②音や光に注意

また、めまい発作が起きると音に対して敏感になるので、大きな音は避けましょう。家族がバタバタとドアを開ける音も、頭に響いてつらく感じます。
部屋は薄暗くしておきましょう。瞳孔系に狂いが生じているので、強い光が目に入るとつらく感じます。
吐き気がつらくて食事ができないときは、無理して食べる必要はありません。
ただ、水分もとれないほど吐き気が強いときには、救急病院などを受診して点滴などを受けたほうがいい場合もあります。
めまい対処法③落ち着いてから、心配なら病院へ

発作後3日ほどはクルクル回るような症状が続くので、静かに横になって過ごします。 家のなかでトイレに行ったり半身を起こして食事をしたりするのは問題ありません。
もし、心配ならば往診してもらえる主治医がある場合は、この3日の間に診てもらうといいでしょう。
往診が難しい場合は3日が過ぎて、症状が落ち着いてから、近くのめまいの専門医(耳鼻科、耳鼻咽喉科に多いです)を受診してください。3日以上経てば、動いたほうがいいのです。
ただし、メニエール病はだんだん進行していく病気なので、いまどの程度の状態なのか、 今後どう治療していくのかを、最初に確認したほうが安心です。ただ、手術が必要なメニエール病はそれほど多くありません。
メニエール病より頻度の高い「頭位性めまい」は、さほど再発率も高くありません。
深刻にとらえることなく、めまいと上手につきあっていきましょう。
めまい対処法④万が一、しびれや麻痺、ひどい頭痛などがあればすぐ病院へ

万が一、めまいと同時に手のしびれ、体の麻痺、強い頭痛、舌のもつれなどがあれば、脳に問題のあるめまいの可能性があります。
大半のめまいは耳に障害が原因で命に関わるものではないですが、
これらの症状があれば命に危険がある「脳が原因のめまい」が起きていることが考えられますので、救急車を呼ぶなどして、すぐに病院へ行きましょう。
めまいの対処法【予防編】

めまいに悩まされない生活のための習慣5つのポイントをご紹介します。
一つ目は、①ストレス
二つ目は、②睡眠
三つめは、③乗り物
四つ目は、④塩分
五つ目は、⑤たばこ です。
①めまいに対処するにはストレスは大敵!

めまいの最大の敵はストレスであるとよくいわれます。
これは、過度なストレスが加わると、自律神経の交感神経が過緊張状態になって、自律神経のバランスが乱れ、めまいを引き起こす前庭神経に影響があるためと考えられます。
また、交感神経が過緊張状態になると、血管が収縮して血流が悪くなって高血圧を招き、 高血圧状態が続くと動脈硬化が進行して、内耳の細い血管も障害されてしまいます。
過度なストレスは、めまいはもちろん、万病の元といわれるほど私たちの健康に影響しています。
普段の生活から精神的なストレスになっている事柄を洗い出し、ストレスを減らすように努めましょう。
②めまいの対処には睡眠も大事

基本的なことになりますが、めまいを起こさないためにはやはり睡眠は大切です。
先ほどのストレスに関係してきますが、十分な睡眠がとれないと、脳や体の疲労を回復することができません。
睡眠は脳と体の休息時間です。十分な睡眠をとるようにしましょう。
睡眠時間はー日8時間以上とったほうがよい、などといわれますが、必要な睡眠時間は人によって異なります。また、熟睡できているかどうかも関係してきます。
十分な睡眠がとれているかどうかは、翌日の朝起きたときに、「ぐっすり眠れた」「疲れがとれた」「今日もがんばろう」など、すっきりと目覚められるかどうかで判断するとよいでしょう。
翌日起きたときに「疲れがとれていない」「なんだかだるい」「まだ寝ていたい」と思うようなら、十分な睡眠をとれているとはいえません。
ここで、めまい対処法における快眠生活のポイントをご紹介します。
快眠生活のポイン卜
- 朝起きたら太陽の光を浴びる
- 朝食を食べて内臓を刺激し、体を目覚めさせる
- 朝は熱めのシャワーを浴びて交感神経を刺激する
- 二度寝はすっきり目覚めにくくなるので避ける
- 日中はしっかりと体を動かして、適度に疲れるようにする
- 休日だからといって昼まで寝たりしない。決まった時間に起きるようにする
- 夕食後の居眠りは眠れなくなるので避ける
- 枕や布団は自分に合った物を選ぶ
- 寝る前のお茶、多量の飲酒、喫煙は避ける
- 寝る前には熱いお風呂に入らず、38〜40度のぬるめの湯がよい
- 寝る前の激しい運動、にぎやかなテレビを見る、ゲームをする、パソコンを使う、 おもしろい本を読むなどは交感神経を刺激して眠れなくなるので避ける
- 寝る前は静かな音楽を聞くなどして心身をリラックスさせる
③内耳に負担をかける乗りものに注意!

めまいの予防、対処するには乗り物のスピードにも要注意です。
私たちはもともと歩いて移動していました。昔の人は、車、電車、新幹線、飛行機など徒歩ではあり得ないスピードで移動することはなかったのです。
これらの速いスピードでの移動も、体、特に内耳にストレスを与えています。なかでも、 飛行機や新幹線での移動は内耳に負担をかけることを知っておいてください。
飛行機は離着陸のときに、ふだんではかからないような加速度がかかりますし、地上からはるか上空に一気に上昇するので、気圧の変化もかなりあります。
飛行機の離陸と着陸、 特に着陸のときに航空性中耳炎を起こしやすいことは、統計上示されています。
とはいえ、「内耳に負担をかけたくないので飛行機に乗りません」などといっていられない場合もあります。
内耳への負担をできるだけ軽くするために、離陸や着陸のときにはアメをなめたり、ガムを嚙んだりして耳抜きをし、耳管の開通をよくしましよう。
鼓膜の内外の気圧の差をできるだけ少なくすることで、内耳への負担を軽くすることができます。
機内サービスで、離陸の後、上空で水平飛行になってからアメなどを持ってきてくれることがありますが、めまい予防にはそのタイミングでアメをなめても遅いのです。
乗り物が原因になるめまいの簡単な対処法として、自分でアメやガムを持参して、離陸や着陸のときになめるようにするだけでずいぶん違うでしょう。
アメやガムがないときには、つばを飲み込んだりして耳抜きしてもいいのです。ちょっとしたことですが、これをしておくのとしないのとでは違います。耳抜きをしなかった人は、目的地に着いたり、家に帰ったりした頃に目が回ってしまう、というリスクが高くなるので、自己防衛のためにもふだんから気をつけてみてください。
この考え方でいくと、飛行機よりも新幹線のほうが加速度や気圧の変化が少ないので内耳への負担は軽いということになります。ただ、トンネル内では気圧の変化があるので、 先ほど紹介したようにアメやガムを利用したり、耳抜きをするようにしましょう。
もともとめまいを起こしやすい人は、移動は飛行機よりも鉄道やバスなど、加速度や気圧の変化が少ないものを選び、耳の閉塞感を覚えたときには、アメやガムなどを活用して耳抜きをして、内耳にかかる負担をできるだけ少なくするようにしてください。
④めまいの対処法には塩分調整が必須!

食事では、ナトリウム(塩分)とカリウムのバランスがポイントになります。
めまいに大きく関わる内リンパ液の成分は、ナトリウムとカリウムのバランスが血液逆転して、カリウムが多く、ナトリウムが少なくなっています。
不思議なことに、これほどバランスが逆転しているのは体液のなかでも内リンパ液だけです。
血液は太古の海と同じpHになっています。私たちの祖先が海から陸上生活へと進化を遂げる途中で、ナトリウムがほとんど存在しない陸上で生活するために、体内にナトリウムを貯蔵するシステムを作り上げたからです。
そして、その過程で、浮き袋やクラゲの平衡石など水中生活で必要だったものを耳のなかに入 れてしまいました。
これに対し、リンパ液など体液は細胞が生存可能な状態に保たれています。ナトリウムが多い状態は細胞に負担をかけるため、リンパ液は力リウ厶が多いバランスに保たれているのでしょう。
血液とリンパ液が、互いにナトリウムと力リウ厶を受け渡してミネラルバランスを保つことで、 私たちの健康は維持できているのです。
塩分の摂り過ぎでめまいに!
現代の食生活では、ほとんどの人が塩分をとりすぎています。血液中の多すぎるナトリウムは体外に排出されますが、そのときにカリウムもセッ卜で捨てられてしまうので、塩分を過剰に摂取する人は、どうしてもカリウム不足になってしまいます。
その結果、内リンパ液のミネラルバランスが崩れ、めまいを引き起こしてしまうと考えられます。
めまい予防のためには、まずは塩分を控えることが大切です。薄味を心がけ、ラーメンは汁を半分残す、みそ汁やスープなど塩分の多いものはー日1回までとする、味付けの濃い料理は避けるなど、減塩を心がけましよう。
自分で作るときには、高血圧対策の減塩レシピを参考にしてもいいでしょう。
もともと、血圧が高くなるとめまいを起こします。これもナトリウムとカリウムのバランスが関係しているのです。
めまいに対処していくには塩分量をしっかり確認していきましょう。
頻繁にめまいに悩まされる人は野菜も食べよう
もうひとつのおすすめは、野菜をたくさん食べることです。塩分を控えるとともに、力リウ厶を積極的にとりましょう。野菜にはカリウムが多く含まれていますし、抗酸化成分も豊富なので動脈硬化はもちろん、老化予防にも役立ちます。
サラダ、お浸し、酢の物、温野菜、マリネ、スティック野菜など、食べ方はなんでもいいので野菜をたっぷりとるようにしましょう。
野菜をとることでミネラルバランスが良くなり、めまいの予防になるのです。
ただし、煮物など味が濃いものは塩分もいっしょにとることになるので、薄味のものを選ぶようにしてください。
⑤めまい予防には禁煙が基本

めまいに悩まされている方で、タバコを吸ってる方はいませんか?
血液の粘性、粘っこさが上がるとめまいによくないことがわかっています。スウェーデンの研究者が、ウサギの内耳動脈を観察する実験を行いました。
このとき、 ストレスのひとつとして、タバコの煙を吹き込んだときの内耳動脈の変化を観察したところ、あっという間にキューッと細くなって、それまでサラサラと流れていた血液がガチガチに詰まってしまったそうです。
よく、タバコを一服吸ったときに、フワーッとしたり、頭がクラッとすることがありますが、これは瞬間的なめまいです。タバコ好きな人は、そのときの気分がいい、だからタバコをやめられないといいますが、それは内耳動脈や大脳の動脈が瞬間的に収縮して、一瞬の酩酊状態に陥っているだけですから、体にいいことではありません。
タバコは百害あって一利なしです。めまいだけでなく健康を維持するためにも、タバコは止めるべきです。
言うまでもありませんが、めまいに悩まされがちな人はすぐにでも禁煙しましょう。タバコを止めるだけでも、劇的なめまいの対処法になることがあります。
▼薬を飲む前に!お勧めのめまい改善法▼