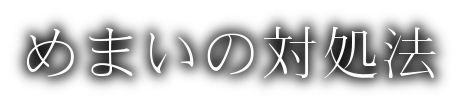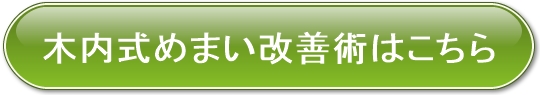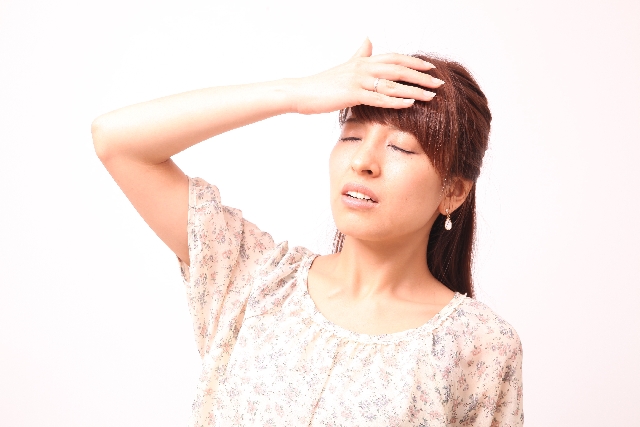
メニエール病は、吐き気やおう吐を伴う、激しい回転性のめまいのほか、耳鳴り、難聴などもあるつらいめまいです。
フランスの医師、メニエールが1861年に「めまいは内耳が原因である」という報告を行い、メニエール病という病名がつけられました。
メニエール医師は、突然の激しいめまい発作を起こして5日後に死亡した少女の解剖結果が、脳になんの異常もなく、内耳に血性の滲出物を認めることから、めまいと内耳の関係に着目したのです。
目次
メニエール病はめまいの半数以上を占める
最初の症例は、いまのメニエール病とは違う病気でしたが、その後、メニエール医師は9例のめまい患者の詳細な報告を行い、内耳に由来するめまいがあることを提唱したのです。
その後、研究が進み、メニエール病はウイルス性の内耳炎など原因がはっきりした内リンパ水腫を除外した、「特発性内リンパ水腫」によるめまいと定義されるようになっています。
特発性という言葉が指す通り、基礎疾患がなく、これといった原因が特定できない内耳の水腫(水ぶくれ)によってめまいが起こります。
激しくつらい発作を伴うメニエール病
メニエール病は、激しい回転性のめまいを何度も繰り返します。
めまいの間隔は個人差が大きく、1日に数回の人もいれば、数週間、数か月に一回、なかには数年に一回など頻度の少ない人もいます。
最初は問題がなくても、めまいの発作を繰り返すたびに聴力が低下していくケースも少なくありません。
生命に危険のないめまいではありますが、受診が遅れると聴覚の異常が戻りにくくなるので、できるだけ早く受診して、適切な治療を受けることが大切です。
メニエール病の原因の水ぶくれ「内リンパ水腫」
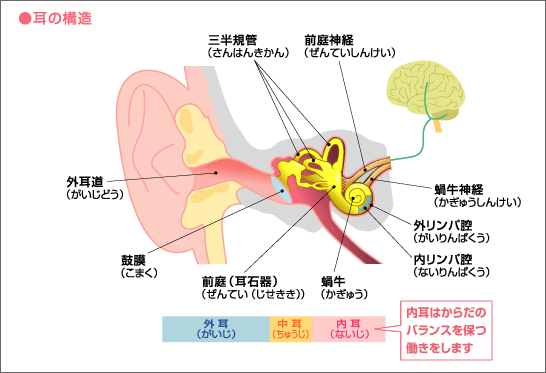
出典:memai-navi.com/chishiki/genin01.htm
メニエール病の原因は「内リンパ水腫」ができるためです。
「内リンパ水腫」ができる要因としては「内リンパ液の過剰生産」もしくは「内リンパ液の吸収障害」が単独、もしくは両方同時に起こっているためと考えられます。
メニエール病は、内耳に「内リンパ水腫」という水ぶくれができることが、めまいの原因となっているのはわかっているのですが、水腫がどうしてできるのかという根本的な原因は、まだはっきりとわかっていません。
メニエール病は女性がかかりやすい病気
疫学調査から推察すると、有病率は人ロ10万人あたり16〜38名程度、男性では40代、女性では30代が発症年齢のピークになっています。
男性よりも女性のほうが多いことは、女性の社会進出によるストレスの影響ではないかと考えられています。
季節は関係ないとされていますが、気圧の谷(周囲より気圧が低くなっている状態)が通るときに、起こりやすいように感じています。
発作は夜間より昼間に起こりやすく、脳や体が疲労しているときにも起こりやすいようです。そのため、精神的や肉体的なストレスが関係していると示唆されています。
症状や聴力検査、平衡機能検査などの結果から診断が下されます。回転性のめまい発作を繰り返し、耳鳴りや難聴などの症状を伴い、神経症状がみあたらない場合はこのメニエール病が疑われます。
メニエール病のめまいに悩んだ有名人

文学や絵画などでも、メニエール病のめまいの苦痛を表現している有名人がいることをご存知でしょうか。
力リバー旅行記の著者であるジョナサン・スウィフトは激しい回転性のめまいに悩まされていたと伝えられていますし、日本でも昭和の文学者、倉田百三がメニエール病であったといわれています。
倉田百三
倉田百三は自身の著書『絶対的生活』のなかで、
「音が次第次第に強く、乱調子になってくる。松風や川瀬の音はいつしかジンジンという音となり、ガンガンという金属製の響きとなり、後には警鐘のごとき音となった(中略)この障害は眩暈(めまい)となって猛然と再現してくるのである」「それらはあらゆる対象が動揺し回転しだした。世界にただの一つも静止しているものがない。大地も畳も波のように動揺する。机上のあらゆる物体、インク壺からペン軸にるまで、本を開けばあらゆる活字が動揺し回転する。それ を耐えることは容易ではなかった」
と、めまいのつらさを書き綴っています。
ゴッホ
ほかに、世界的にも有名な画家、ゴッホの晩年は、精神病ではなくメニエール病であった可能性が考えられます。
ゴッホが妹に宛てた手紙には
「いつもクラクラとめまいを感じた」
弟への手紙には
「今月の初めに始まった縦ゆれ」
など、めまいの症状を連想させる記述があるそうです。
また、ゴッホの作品のひとつ『星月夜』は星が左から右に流れ、波が渦巻くように回旋しています。これは、メニエール病の発作で右向きの眼振(眼球の揺れ)があったときに見た星空の印象を絵にしたのではないかと言われています。
ゴッホで有名な事件である自分の左耳をそぎ落とすという行為も、発作時の耳の閉塞感や、 耳鳴りなどの不决さをがまんできなくなり、耐えきれずに左耳を傷つけたのではないかと考えられています。
このように、メニエール病は長く患うと聴覚に異常をきたし、耳鳴りが四六時中続くという非常につらい症状を引き起こします。ときには耐え難い苦痛となるので、早期に適切な治療を受けることがとても大切です。
治療方法

メニエール病の治療は薬物療法が中心となります。
薬物治療によるめまい改善
メニエール病の原因となる内リンパ水腫ができるのは、「内リンパ液の過剰生産」もしくは「内リンパ液の吸収障害」のためと説明しましたが、治療の基本となるのは内耳の血流改善作用がある抗めまい薬です。
これは内リンパ水腫による損傷の改善や苦痛の軽減に役立つだけでなく、内リンパ水腫ができないようにするための予防にもなります。
めまいの薬物療法には、このほかにも、 自律神経薬、抗ヒスタミン薬なども用いられます。
内リンパ水腫は内耳のむくみとも考えられるので、水分のとりすぎや塩分の過剰摂取を控えてもらい、利尿薬を用いることもあります。
処方される薬の例
- メチコバール
- メリスロン
- メニレット
- プレドニン
- トラベルミン
- ナウゼリン
- セルシン 等
手術
薬物療法やストレスを軽くするための心理療法、日常生活の改善などでは症状が軽減されず、持続期間が長く、めまいの発作が多い場合には、手術が検討されます。
入院は3週間程度で、めまいや難聴の改善に効果がある手術なので、症状がひどいときには選択肢のひとつとして考えてもよいのではないでしょうか。
メニエール病によるめまいの対処法
めまいの発作期の対応
発作の最中や直後はとてもつらく、動けるような状態ではないので、救急病院を受診したり、往診を頼んだりしましょう。
近所の内科医を受診したり、めまいの専門医を受診することは難しいケースが多いです。症状が悪化しないよう安静に過ごすことが大切です。
急性期の対応
急性期は発作が治まってから3〜7日間、長くても14日までです。
グルグル回転するようなめまいは治まっても、平衡機能はまだ不安定なので無理は禁物です。できればこの期間に、近くのめまい専門医を受診しましょう。
発作が治まってきてしばらくしてからの対応
発作が治まってきてからの亜急性期になると平衡感覚の不安定さが改善し、聴力も戻り始め、耳鳴りが軽くなります。 発作が再発しなければ約3か月間。この時期は内リンパにたまっているリンパ液を排出するために、薬物を使った減圧療法が行われます。
間欠期の対応
めまいの発作から一定に期間をおいた間欠期は内リンパ水腫の予防と、内リンパ水腫によって損傷した細胞や組織の修復が治療の主な目的となります。血液の循環をよくする一般的な抗めまい薬が治療の中心です。
場合によってはビタミン剤や抗うつ薬などが処方されることもあります。
最後に
めまいの発作が起こったときにはとてもつらいメニエール病ですが、薬物療法や手術によって症状を抑えたり、苦痛を改善したりすることが可能です。
めまいぐらいでと軽くとらえず、早めにめまいの専門医を受診して適切な治療を受けましょう。